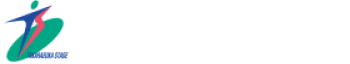Chapter 01
舞台と無縁のくらしから一転
「ものづくりが好きで、学生時代は彫刻などの立体造形を学んでいました。実は入社するまで宝塚歌劇は一度も見たことがなかったです。」そう笑いながら話してくれたのは、2006年入社の下農(しもの)さん。舞台の世界観を演出する上で欠かせない小道具係に所属している。 「就職活動の際は“ものづくりができたらいいな”とぼんやりと考えていたくらい。2学年上の先輩が宝塚舞台に入社していたので、ちょっと受けてみるか…くらいの軽い気持ちでした。だから、筆記試験で宝塚歌劇についての設問が出たときには、落ちたな…と思いましたね(笑)。」と当時を振り返ります。 舞台とは無縁のくらしから一転、入社後のギャップはなかったのだろうか?
Chapter 02
強度と軽さを求めて、ミリ単位で調整
「小道具という名前から、銃や剣などの手持ちサイズのものの製作を想像していたので、机などの大きな家具も担当することと、公演業務があることは少し驚きました。」と下農さん。 小道具係は入社してすぐは公演業務を担当する。 公演業務を通して“舞台でどのように小道具が使われているか”を自分の目で見てはじめて、どのようにつくれば出演者が使いやすいか、自分たちが運用しやすいかが分かるからだ。 「宝塚は出演者が全員女性なので、銃や剣一つとっても“重さ”がネックになってきます。持つだけでなく、そのまま歌ったり踊ったりしますからね。さらに、宝塚大劇場と東京宝塚劇場の約3か月間の公演の間、使い続けられる強度も必要。“軽さと強度”は僕たちの永遠の課題です。」と下農さん。 軽さをとると壊れやすく、強度をとると重くて扱えない。どちらも担保できる塩梅をミリ単位で探りながら、世界観も表現するのは骨が折れる作業だろう。
Chapter 03
生涯現役でものづくりの現場に
小道具係は宝塚舞台の製作系の係のなかで唯一、デザインを担当できる係だ。コーディネーターといって、公演につき1名選出され、演出家との打ち合わせからデザイン出し、予算管理、初日から千秋楽までの公演のオペレーションを担当する。用意する小道具は、新たに製作するもの、購入するもの、リメイクするものなど含め、数百点にも及ぶという。 「初めてコーディネートを担当したのは2011年でした。いつかはコーディネーターをやりたい!とは思っていたけれど、いざ担当するとプレッシャーは半端なかったです。」と下農さん。和物の作品だったため、打ち合わせで出てくる道具の名前や、色の指定が初めて耳にするものもあったと言います。 「行李(こうり)など、現代ではあまりなじみのない物もあり、製作では苦労しました。パリと日本を行き来する作品だったので、両国の資料を調べながらつくったことを覚えています。」と当時を振り返ります。技術は手を動かすほどに上達するが、知識は自分で取りに行かなくてはいけない。多種多彩な演目を行う宝塚ではなおさらだろう。提案の幅を広げられるよう、様々なカテゴリーの映画や資料を見て、引き出しを増やしたと言います。 「でもね、20年近く小道具をしていますが、いまだに打ち合わせの時に聞いたことのないワードが出てくるんですよ(笑)。本当に刺激的で勉強の毎日です。新入社員の子達にもこの楽しさを感じてほしい。これからも現状に満足せずに、生涯現役でものづくりの現場にいられたら嬉しいですね。」。そう話す下農さんの横顔は、希望に満ち溢れていた。
time schedule
タイム
スケジュール
<1回公演の場合>
-
09:30
出勤・係でミーティング 製作作業
-
10:00
公演のための道具点検・掃除
-
11:00
製作作業再開
-
12:00
昼休憩
-
12:50
公演準備
-
13:00
第1幕開演 公演業務
-
14:30
第1幕終演後、第2幕に向けてセットチェンジ
適宜小休憩 -
15:00
第2幕開演 公演業務
-
16:00
終演後、片付け
製作作業再開 -
18:10
片付け
-
18:30
退勤
meaasege
求職中の方に
メッセージ
舞台を見たことがない、ものづくりをしたことがない人でもやる気があれば大丈夫。舞台の知識や技術力は入ってからいくらでも身につけられます。小道具は演出家との打ち合わせからデザイン、製作、公演業務まで携われますし、外部公演業務で出張することも。マルチに色々できる係なので、毎日飽きることがありませんよ!